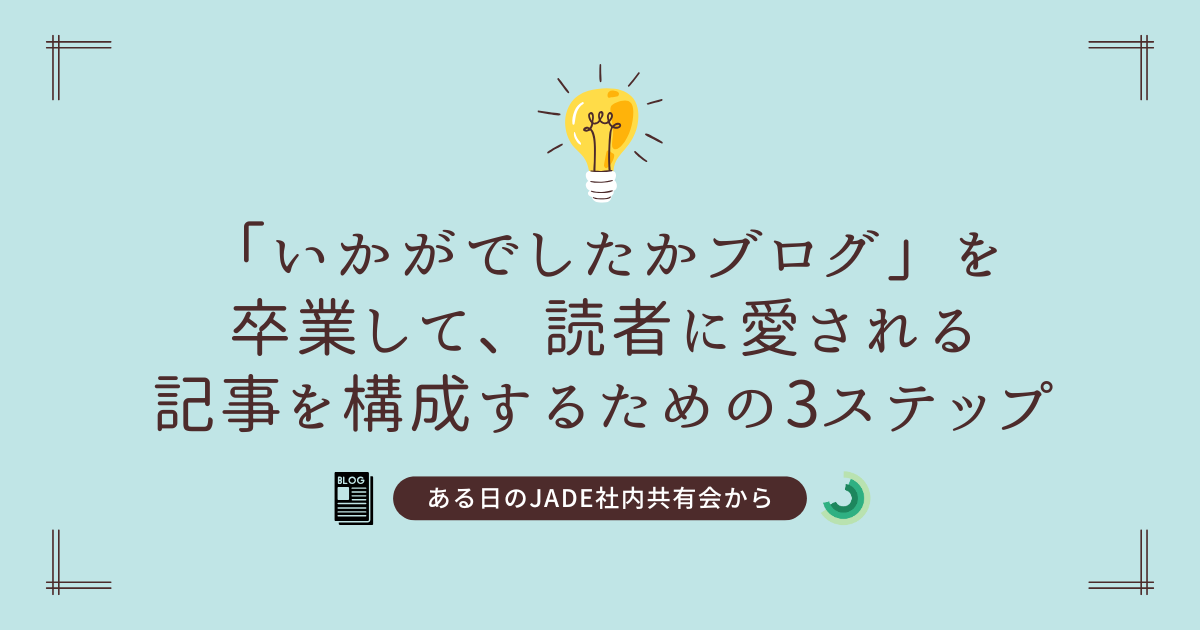
「何にも書いてないやん」
「読んでて得るものがない」
検索でヒットした記事を読んでいて、思わずブラウザの「×」ボタンを押したくなる瞬間。誰しも経験があるのではないでしょうか。
JADE社内で開催されたコンテンツ企画構成の共有会で講師を務めた垣本が投げかけたのは、まさにこの現代Web記事の課題でした。検索結果を見渡せば、コピペのような似たり寄ったりの記事が並ぶ現状。しかし本当にユーザーの検索意図を理解し、期待を超える価値を提供できれば、検索上位表示はもちろん、読者から愛される記事になれる——。
今回は、その講義で共有された「中身のあるコンテンツ」を作るための実践的な手法の一部をご紹介します。
講師を務めてくれたメンバー
垣本晴美 広告運用のスペシャリストであるのみならず、ユーザーの検索行動全体を俯瞰するコンテンツ設計の専門家
小坂奈保美 代理店・インハウスで豊富な経験を持ち、検索エンジンの仕組みから検索ユーザー体験まで一気通貫で最適化を手がけるSEOとデジタルマーケティングのプロ
「コタツ記事」はなぜ読者をイラつかせるのか
「皆さん、自分で何か調べ物をしていて、なんらかのページを見に行き、イラっとしてページを閉じたことってきっとありますよね」
この言葉から始まった共有会で、まず明確にされたのは敵の正体でした。
現在のWeb上には「いかがでしたかブログ」や「コタツ記事」と呼ばれる記事があふれています。これらに共通するのは以下の点。
- 想定読者の意図の深掘りが浅い
- オリジナルの情報がない
- ただキーワードを詰め込んだだけの内容
「私たちとしては、ユーザーをイラっとさせる記事は出したくない。これがコンサルタントとしてのプライドであり、必要な姿勢です」
垣本の口調からは、技術うんぬんより「プロとしてのプライド」がビシビシ伝わってきます。では、どうすれば読者に価値を提供できる記事を作れるのか。そのヒントが、次に紹介する3つのステップです。
ステップ1:検索結果は「ユーザー心理の宝庫」
検索結果画面に隠された手がかりを読み解く
まず目を向けたいのは、検索結果そのものが持つ情報の豊富さです。
「コンテンツは、なんとなくでも作れてしまうものです」と垣本は指摘します。しかし、なんとなくで作った記事では、クライアントから「どうしてこういうセクションが必要なんですか?」と問われた時に明確に答えることができません。
そこで重要になるのが、検索結果の徹底分析です。
強調スニペットは「答えの核心」
検索結果の上部に表示される強調スニペットには、そのキーワードに対してユーザーが最も求めている答えが凝縮されています。「あれはユーザーの検索意図に対して最も端的に答えられる言葉、文章が出てきたはずです」——ここから基本的な検索意図を読み取ることができます。
広告枠は「行動意図」の鏡
広告の表示状況も重要な手がかりです。「ショッピング広告枠が出てくるなら、その言葉で検索している人は購買意欲が高そうです。また、商品を購入するのではなく、資料請求をして情報を集めたいというニーズを持った検索行動もあります。」このように、広告はユーザーの購買意欲や求めているアクションを探る大きなヒントになるでしょう。
「他の人はこちらも検索」は潜在ニーズの入り口
関連検索や「よくある質問」セクションは、さらに深いニーズを探る手がかりになります。「そのキーワードで満足できなかった人がいたとしたら、どういう言葉で再検索しているのか。それが、その人たちの本当のニーズを想像する手がかりになります」
競合分析は「共通点」と「独自性」の両軸で
「私がコンテンツの企画、記事構成を作る時は、検索結果の1ページ目に出る記事はすべて目を通します。これは皆さんも実践されていると思いますが、私が大事にしていることは以下2つです」
1. 共通要素の抽出
「すべての記事に必ず書いてあることは何か?」——これらは、そのキーワードで検索するユーザーに対して絶対に答えるべき内容です。
2. 独自性の発見
「特に上位に出ている記事は、オリジナリティのある情報を載せていたり、『そういう発想はなかったな』というセクションが書かれていたりします」——ここから差別化のヒントが見つかります。
ステップ2:データはユーザーの「隠れた物語」
Yahoo! DS.INSIGHTが明かすユーザーの真実
検索結果だけでは見えてこない、より深いユーザー像を理解するために重要なのが外部データの活用です。
「個人的にはYahoo!のDS.INSIGHTがとても好きなので、コンテンツを考える時にDS.INSIGHTは必ず見ます」
【DS. INSIGHT活用についての参考記事】
垣本がここまで入れ込む理由は、データから読み取れる「ユーザーの物語」にあります。
仮に、「肌荒れの改善」で検索するユーザーが1年前に「スキンケア方法」について調べていた場合、「肌の悩みは、1週間や2週間で終わる悩みではないことが見えてきます」と垣本は説明します。
でも、ここで注目すべきはもう一つの側面です。検索キーワードが「スキンケア方法」から「肌荒れの改善」に変化している——これは単に悩みが長期化しているだけでなく、ユーザーの問題認識そのものが変化していることを示しています。
1年前は「正しい方法を知りたい」だったのが、今は「改善したい」。つまり、基本的な知識はもう持っているけれど、それでも解決しなかった人たちが検索しているのではないか。こうしたユーザーに対して、再び基礎的なスキンケア方法を並べても「それはもう知ってる」となってしまう。求められているのは、一歩踏み込んだ解決策なのかもしれない、と仮説を立てます。
【参考記事】
季節性キーワードの「波」を読む
Googleキーワードプランナーから得られる季節性データも、戦略的な判断材料になります。
例として、とあるキーワードの分析が紹介されました。
「2024年だと9月に検索がすごく増え、その後減少していることが分かります」
このデータから、秋にこの悩みが深刻化する傾向が読み取れ「このキーワードに関するコラムは、秋に合わせてリリースしていくと良いのでは」という戦略的な判断ができるようになります。
クライアントとの対話で「現場の声」を拾う
一方で、データだけでは限界があります。「特に、自分が利用者になりえない商材に関しては、クライアントとよく会話を重ねてほしいと思います」と垣本は強調します。
この発言の背景には、データ分析だけでは見えてこないユーザーの実態があります。たとえば、BtoB向けの業務システムや専門性の高い金融商品など、一般的なライターが実際に体験する機会のない商材では、検索データから読み取れる情報と現実のギャップが大きくなりがちです。
営業担当者が「よくこんな質問をされます」と言う内容と、実際の検索キーワードが一致しないケースも珍しくありません。また、お客様が口にする表面的な要望の奥に、本当に解決したい課題が隠れていることも多いのです。
だからこそ、日々お客様と接している現場の人たちからの生の声が不可欠になります。
ヒアリングで得るべき情報:
- 実際の顧客像と、抱えている課題
- お客様からよく聞かれる質問や相談内容
- 自社の強み・弱みと競合との違い
- 導入後にお客様が予想外に評価するポイント
- 逆に、期待していたのに満足度が低かった機能や要素
ステップ3:「流行り廃り」をヒントにする
文章にも「流行」がある
「人が読む文章には流行り廃りがあると思います」
私たちも無意識のうちに「読みやすい文章」の基準が変わってきているのではないでしょうか。
例えば、最近は以下のような文章をよく見かける印象です。
- 会話調で読みやすい
- 結論が先に提示される
- SNSのように短文で構成されている
若年層向けのコンテンツでは、「なるべく短い文章で分かりやすくカジュアルに、大事なことだけ書く」ことが重要になるかもしれません。ターゲットの属性、置かれた状況などにあわせて、ベストな文章は変わるはずです。
タイトルの進化が物語る「読者の変化」
昔の小説のタイトル『雪国』のような抽象性と、現在の『俺だけレベルアップな件』のような具体性。この変化から、読者の消費パターンの変化が見えるかもしれません。
「X(旧Twitter)などを見ていても、140字の文章ですらGrokで要約してほしいという声がありますよね。文章を読みたがらない人もたくさんいる、ということは頭に入れておきたいです」
タイトルを見ただけで内容が理解できる明確性は、今後も求められていくでしょう。
SNSの「見方」を変えてみる
「SNSなども、見ておくに越したことはないですね」。SNSは誰でも見ているものですが、垣本が言いたいのは「見る視点を変えること」。
普段は友達の投稿や好きなインフルエンサーの発信を楽しんで見ているSNSを、今度は「コンテンツ制作者」の目線で眺めてみる。すると、いつもとは違うものが見えてきます。
- なぜこの投稿は2万いいねもついているのか?
- 炎上した投稿の「何が」人を怒らせたのか?
- フォロワーが多い人の文章は、どんな「型」があるのか?
「コンテンツを提案するものとして、こうしたトレンドはきちんと押さえておく必要がある」——つまり、いつものSNSの見方を「観察」に変えることで、読者に響く表現のヒントが見つかるのかもしれません。
プロが見る「記事品質」の4つの判断基準
小坂は数多くのコンテンツレビューを通じて見つけた、品質の高い記事に共通する要素を共有してくれました。
1. 検索意図をちゃんと分かっているか
「何はなくとも、まずはターゲットクエリの検索意図がすべてだと思っています」
小坂が最重要視するのがこれ。表面的に「こういうことを知りたいんだろうな」じゃなくて、「もう一歩踏み込んだ潜在的な検索意図で、見落としがないか」まで考えられているかどうか。
2. 読む人の顔が見えているか
同じキーワードで検索しても、人によって求めているものは全然違います。そのキーワードを用いる検索ユーザーにとって最も情報が受け取りやすい文章や構成はどのようなものか?を考える必要があります。
- 初心者なのか、もう詳しい人なのか
- 急いでいるのか、時間をかけて調べたいのか
- 具体的な方法を知りたいのか、まず背景を理解したいのか
3. 競合研究、きちんとやっているか
「競合サイトで評価されているであろう点が、自社の記事にも反映されているか」——上位に出てる記事がなぜ評価されているのか、その理由を自分の記事にも活かせているかということ。
4. 読後にどんな行動をとってほしいのか
この記事を読んだ人に、最終的にどんな行動を取ってもらいたいのか。その目的がはっきりしていて、現実的に達成可能かどうか。また、その態度変容がサイト全体の目標に寄与するものかも重要な判断基準です。
読者のことを本気で考えているかどうか——結局のところ、それがすべてなのかもしれません。
「よくある疑問」に現場のプロが答えます
共有会の最後に、参加したメンバーからの質問をいくつか紹介します。
Q. デバイスで記事構成は変わる?
A「サービスによって、利用されるデバイスは大きく異なります」
PCユーザー: 落ち着いた環境で詳細比較。複雑な図解や比較表も有効
スマホユーザー: 移動中の短時間利用。簡潔な見出し、読みやすいレイアウトが重要
Q. 記事構成にかける時間は?
A「そのコンテンツが全体戦略の中で、どのくらいパワーをかけるべきなのかが重要なので、かける時間はコンテンツや戦略によって全く異なります」
重要度の高い記事には数日をかけることもあり、「場合によってはお客様を巻き込むほどパワーをかけることもあります」。
Q. 効果測定はどうしている?
A「広告のように、どの部分が良かった、悪かった、と特定することはできません」としながらも、段階的な分析方法があります。
- 意図したクエリでヒットしているか
- 順位とクリック率の関係
- 記事からの回遊状況
「数字を見て断定することはできませんが、いくつかの情報から『おそらくここが良くないのではないか』と想像することはできます」
SEOを忘れた時、本当のSEOが始まる
共有会の最後で参加メンバーから出た「SEOを考えずに記事を書くのが正解」という発言に垣本も小坂も強く共感していました。
検索エンジン最適化のテクニックに走るのではなく、ユーザーの悩みや疑問に真摯に向き合い、期待を超える価値を提供すること。それこそが、結果的に検索上位表示につながる道なのです。
「この記事を読んだ人がイラっとして離脱しないか」
「いかがでしたかブログ」を撲滅し、読者に愛される記事を生み出すために、わたしも常にこの問いを自分に投げかけたいと思います。