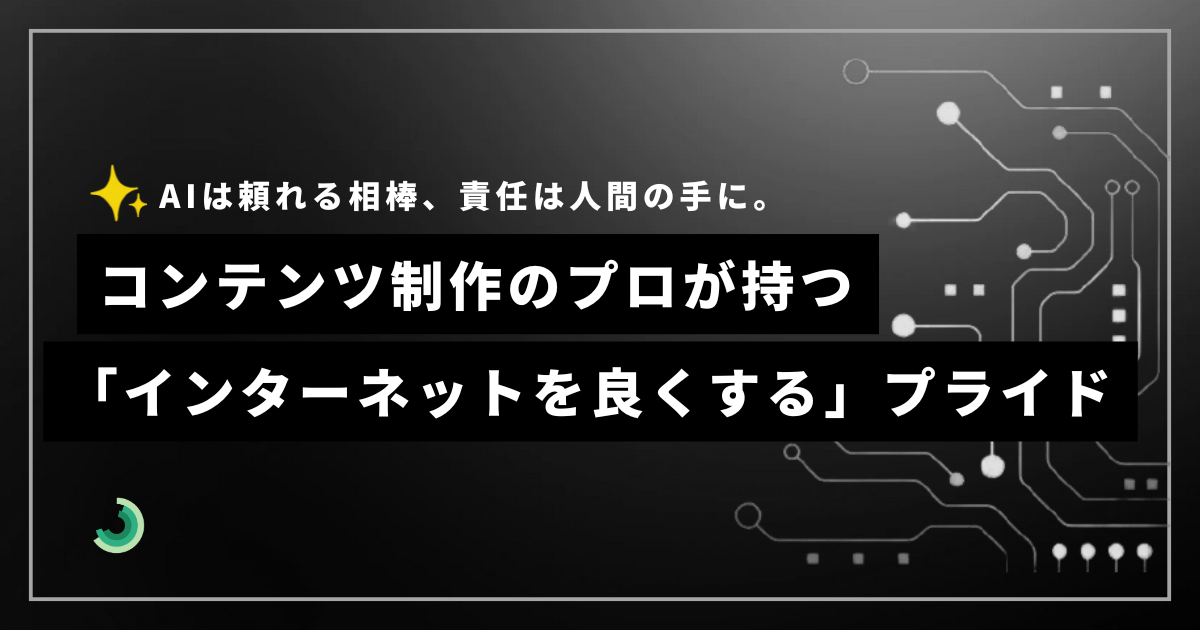
「AIで記事を書いたらもっと楽になるんじゃないか?」
そんな期待を持ってAIツールを導入したものの、実際は「あれ? なんだか前より忙しくなった気がする……」と感じている方、いませんか?
今回は、コンテンツ制作の現場で日々奮闘するJADEのプロフェッショナル2名に、生成AIとの付き合い方について本音で語ってもらいました。JADEのメンバーが語る「AIと人間の適切な役割分担」や「プロとしてのプライド」とは、果たして――。
【もくじ】
参加メンバー:
- 垣本晴美 広告運用のスペシャリストであるのみならず、ユーザーの検索行動全体を俯瞰するコンテンツ設計の専門家
- 藤井晴香 さまざまな分野でのSEO経験を活かし、ディレクションから戦略設計まで手がけるコンテンツ制作のプロ
AIを使い始めたら、逆に大変になった?
「『AI、早く私の仕事を奪ってくれないかな』って冗談交じりに言っていたんですけど、実際に本格的にコンテンツ制作で使い始めたら、かえって大変になったんじゃないかなって感じていて。経営層との面談の時に『それを記事にしたら良いのでは』という話が出たのが、今回の対談を持ちかけたきっかけです」
そう話すのは、JADEの中でもコンテンツ制作でクライアントを支援することが多い藤井です。提案の品質は上がったかもしれませんが、人間の業務が増えていないか?と感じているそうです。
現在JADEが関わっているコンテンツ制作ですが、記事コンテンツの提案や、季節性商品の特集ページアドバイスなど、案件の幅は多岐にわたります。過去にはチームメンバーであるサイトのタイトルやディスクリプションを大量に作成していた時期もあったそうです。
コンテンツに関わるメンバーはJADEの中では決して多くなく、現在は若手メンバーへの指導も進行中とのこと。「意外とJADEでコンテンツ制作に携わったことがある人は少ないんです。やろうと思えばできるであろう方はたくさんいらっしゃいますが」と藤井は現状を説明します。
「個人的には、JADEのコンテンツ制作の方法はそれなりに体系的になっていると思います。フォーマットがしっかりあるので、必要な作業をこなせば基本的なレベルのものは誰でも作れる設計になっている。ただ、最低ラインから100点に近づけて競合を追い抜くレベルになると、やはり個人の能力差が出てくるポイントですね」と垣本。
こちらの記事を読んでいただくと、垣本がコンテンツ制作をどのように捉えているのかをわかってもらえると思います。
2人がAIには難しいだろう、と言うのがクエリの選定。「お客様が『このクエリを狙いたい』とおっしゃった時に、上位表示の実現可能性がどの程度か、という判断は、経験がないとできません。AIにも難しいと思います」と声をそろえます。「AIに『このクエリで上位を取れますか』って聞くと、AIは寄り添ってきて『取れます』って言うんですよ(笑)」
💡 皆さんは、生成AIの導入による効率化、どう感じていますか?
JADEメンバーのAI活用術と使い分け
では、実際に現場ではどのようにAIを活用しているのでしょうか?
垣本は「自分が作った構成案をAIに読ませて『これを100点にするには何が足りない?』『もう少し考えを足すとしたらどこ?』って聞いて、磨き上げるために使っています」と話します。
藤井も「ユーザー像の調査は自分でやりますが、基本データだけ渡して『どんな背景があると思いますか?どんな属性ですか?生活はどんな感じですか?』って投げかけると、自分にはなかった引き出しを開けてくれます。これは特にClaudeが得意とするところかなと思っています」と活用法を共有。
ただし、「取り入れるかどうかは人間が判断するので、そこが難しいところではあります」と藤井。特に価値を感じているのは、検索結果の1ページ目にない情報を提供してくれる点だと言います。垣本も「検索結果の外に出ないと、質の良くないものを生産するだけになってしまいます」と語ります。
時短効果については、2人の実感は少し差があります。垣本は「個人的には結構時短できている感じがします。情報をとにかく取ってきて並べるような、手さえ動かせばいい単純作業は本当にAIにしてもらうべきだと思います。でも、競合記事を読み込んで『この記事はここのセクションがすごくいい』とか、逆に『この記事は意味があるのか』みたいなことを言語化する時間は何も減っていません」と話します。
一方、藤井は「今のところそんなに時短できている感じはないんです。AIの頭が良すぎて、自分がそこについていけていないというか……取ってきてもらった情報を自分が読み解く時に『難しいな』となってしまったり、自分の知らない情報を持ってきた時のファクトチェックに時間がかかります」と率直な感想を語ります。
インターネット上に情報が出揃っている商材かどうかによっても効果は変わるようで、藤井は「出揃っているものだったらNotebookLMを活用して商材理解に努めたり、自分の目視でどうしても見落としてしまうこと(上位記事の共通点や差別化ポイントなど)をピックアップしてもらうのにすごく便利」だと感じているそうです。
藤井がメインで使っているのはClaudeですが、「返ってくる文章が硬く、専門書のような印象が多い。同じプロンプトをGeminiとClaudeに投げてみると、Geminiの方がひらがなが多くて易しい、インフォメーショナルクエリの検索結果でよく見るような構成案を出してくれます」と特徴を分析。改善方法として「簡単な文章でもっと短くして」と指示して調整しているそうです。
垣本は「個人使用ではChatGPTが大好きで、業務ではGeminiの方を圧倒的に使いますね」と使い分けを明かします。「『ちょっと面白いこと考えてよ』『普通のコンテンツは嫌なんだよね』みたいな話をGeminiにすると、『ユーザーが面白く読めるようなセクションあった方がいいんじゃない?』『こんなのどう?』って提案してくれます。面白さの点では、ClaudeよりGeminiの方が能力が高い気がします」。
ただし、「プロンプトにもよると思いますが、広告文を作ってもらう時はClaudeの方が好き。『全角15文字をなるべく限界まで使って作って』って言うとClaudeの方が的確で良いものを出します。Geminiだと、同じプロンプトでも8文字くらいで出してきたりして『ちょっと微妙だな』と思うことがあります」と適材適所があることも指摘。
垣本はAIとの会話が盛り上がって時間がかかることもあるそう。「例えば『モチベーションの低い人が離脱しない仕掛けを考えて』って投げると、『診断コンテンツはどう?』みたいに返ってきて、その診断のロジックも一緒に詰められたりします。私はAIが好きで、AIとの会話が盛り上がって時間がかかることもありますね(笑)」
藤井は「確かにClaudeの使用にこだわりすぎていたかも。Geminiでブレスト的な使い方をしていなかったので、今度からやってみよう」と、垣本との会話からヒントを得ていました。
ChatGPTは「情報の構造化が圧倒的に優れています。見出しを分かりやすく出して、簡潔に説明文が入って、必要なら表を作ってくれる。ぼんやりした頭にも入りやすいんです。GPTからの返事を見て『文章はこういう風に整理した方がいいんだ』って学びますし、メールの添削もしてもらっています」(垣本)
藤井も「プライベートで使うのはGPTかな」と同意し、垣本も「さっき言ったように、おしゃべりが楽しい」と付け加えました。
| AIツール名 | 得意なこと/特徴 | 主な活用法 |
|---|---|---|
| Claude |
|
|
| Gemini |
|
|
| ChatGPT |
|
|
コンテンツ制作者としてのプライド
💡 あなたのコンテンツ制作に、これらのAIツールをどのように活用できそうでしょうか?
ここで話題は核心に迫ります。プロとして、AIとどう向き合うべきなのか?
「1位から10位までの記事をガッチャンコしたキメラが上位表示されやすい時代はあったとは思いますが、もう終わったかと」と藤井は語ります。現在は、いわゆる“ドメインパワー”やh2・h3の装飾に頼らず、「一人の経営者がつらつらと書いた日記みたいなものがすごく読んでて面白くて1位とか2位に表示されている」ケースも多いそう。単純な情報の合算だけでは勝てない時代になったということです。
だからこそ、プロフェッショナルとしてのスタンスが重要になります。「プロンプトをいくら練って作ったとしても、AIに『これらの情報から記事構成を作ってください』って投げて返ってきたものを、自分で目視で修正していきます。『あなたはここにこの見出しを入れているけど、それは何ですか?ユーザーの理解の順番に合っていますか?』って逆質問すると、『申し訳ございません』って謝られることがあります(笑)」(藤井)
また、「一企業人として、AIに全部任せてそれを納品物としてアウトプットしたら、クライアントに責任が持てません。ライターから『なぜこの見出しの次にこれを書くんですか?』と聞かれた時、AIまかせでは答えられない。自分の納品物だと言えるくらい手をかけたものをクライアントに渡したい」という気持ちがあると語ります。
垣本も「AIが提案したものと同じになっても構いませんが、すべての見出しや順番、使った言葉について説明ができるべきです。説明できないセクションなら削ってしまえばいい。なぜここにこれがこの言葉で必要なのか、という根拠を持って並べることが重要です」と強調しました。
「あるクエリで上位に表示されている記事だからといって、それが優れたコンテンツとは限りません。他に表示させるべき良いコンテンツがないから仕方なくGoogleが表示しているということもあります。これはGoogle検索の仕組みを知った上でたくさんの検索結果を見てきた人間でないと気付けないポイントです。」(藤井)。垣本も「順位を見ていって、下の方まで行くと、二番煎じのコンテンツになってしまうクエリってありますよね。そういうときは『価値のあるコンテンツが少ないクエリなんだな』って思います。そういうのを見つけると『よし、やるぞ』って思うんです」と話します。
JADEでは「インターネットをより良くするコンテンツでなければ提案しない」という強い信念でコンテンツ制作に取り組んでいます。
藤井は「誰かのために」という視点の重要性を強調します。「コンテンツディレクションの仕事をしていると、ターゲットクエリが自分と馴染みがなくて悩まされる場面が多々あります。でもあるとき気付いたのは、仮に“経営コンサル 選び方”というクエリがあったとして、それを読んで経営コンサルを導入してみようかなって思う事業主がいるかもしれない。私がそうやって開業されたお店の常連顧客になるかもしれない。いくらB2Bの難しいクエリであっても、その先にいるのは一般消費者であって、私たちかもしれないんです。クレーン車やベルトコンベアなどの『どうしたらいいんだ……』と思うような産業機械のコンテンツを頼まれたとしても、その消費の末端にいるのは私たちです。一般消費者と無関係なクエリなんてないので」
「流入数を増やすためのコンテンツではないんです。検索ボリュームが少ないクエリでも対応することがあります」(垣本)
仮に月間30しか検索ボリュームがないクエリでも、例えばビジネスにおいて重要なユーザーが、意思決定に関わるタイミングで検索するクエリであれば、そこに価値あるコンテンツを出すことに意味があるという考え方です。
具体的なエピソードを垣本が話してくれました。
「単純に検索ボリュームの多いクエリから提案してしまうと、『このコラムに何の意味があるんですか?』という話になりがちです。なので『ユーザーの意思決定に関わるクエリはおそらくこれで、悩みの深刻度も高く見えます。正しい知識を提供するコンテンツが検索結果上にあるべきだと思います』という提案をすると、『本質的ですね』とおっしゃっていただいた経験がありますね」
💡 あなたのコンテンツ制作において、AIと人間の最適な役割分担は何だと思いますか?
インターネットを良くする、AIとの理想的な連携
対談の最後に、藤井が気づきを共有してくれました。
「これはあくまで主観ですが、テクニカルなSEOに長けた人材と比較して、コンテンツ制作を中心にSEOに携わる人間の方が、自分のスキルを低く見積もってしまう傾向があると思います。私がそうなんですけど。でも今日垣本と話してみて、『なんだ私、この仕事にプライド持ってるじゃん』って気づきました」
「プライドを持ってこの仕事をやっているし、立派にインターネットを良くしているなって思い直しました」
AIはコンテンツ制作者から仕事を奪う敵ではもちろんなく、より良いコンテンツを作るための相棒だということが、対談ではっきりと浮かび上がりました。
2人のプロのプライドを言語化しておきましょう。
- AIの力を借りながらも、最終的な判断と責任は自分が持つ
- インターネットをより良くするという使命感を忘れない
- 検索する人のことを第一に考える
- すべての要素について説明できるレベルまで理解する
コンテンツ制作の現場はAIの進化とともに変わりつつありますが、人間ならではの価値観や判断力、そしてプロフェッショナルとしてのプライドは、これからも重要なまま変わりません。
AIは相棒。でも、責任を持つのは結局、私たち人間なのです。
この記事があなたのAIとの向き合い方を考えるきっかけになれば幸いです。コンテンツ制作に携わる皆さん、一緒により良いインターネットを作っていきましょう!